箱入り |
 by by 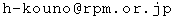 2022.12.19. 2022.12.19.お断り書き: 作品中にWEMAという略号が出てきますが、同じ略称を使う他の団体や装置とは全く関係ありません。 9400字あります、他の作品より少々長めです。 いつもの1日が始まった。 浦島君の目覚めを感知したセンサーが室内の明かりを昼用にセットし直した。ベッドから起きると、エアーコンディショナーが部屋の空気を感知して、ファンを二段階強くした。室内のチリと匂いは機械に吸引され紫外線分解される。一昔前の様に部屋の空気を外気と入れ替える必要はない、室内の空気は外気よりもはるかに清潔なのだ。 寝起きの体をストレッチして、ルームランナーに乗り、VRゴーグルをつけて軽いジョギングをする。昨日の続きでバルセロナを走る事にする。ディアゴナル大通りを東向きに進む。共有レベルを3にしているので、他に走っている者は数人しか居ない。たった一人で走るのはつまらないし、多すぎてもうっとうしい、これくらいの人数が一番良い雰囲気だ。 ひと汗かいてシャワーを浴びたら食事だ。今日の朝食は野菜サラダ、サバ味風味の魚肉。ジョギングの間に食用3Dプリンターで造られた物がテーブルの上にセットされている。スープは自分の好みに合わせてみそ味にした。プリンターの具剤が足りているか確認してみる。室内埃や排泄物を分解した物が具剤に使用されているが、どうしても不足する部分が出てくるのは避けられない。ステーキ味を楽しむためには、タンパク・アミノ酸の一部が残り少なくなっているようなので、マークを入れておく。 食事の時間はたっぷり取った。 そして、今日は会社勤務の日である。仕事はVRリモート、今日は会議室に行って、来月のプロジェクトの打ち合わせ、という事になっている。VRゴーグルを付け位置情報をセット、会社の玄関に立つ。玄関からホールを進み、エレベーターに乗って最上階に上がり、会議室に入って着席する。隣に座ったアバターは見かけないフォルムだが、たぶんカオリだろう。一応確認のため「ハイ、カオリ」と声をかけて反応を見る。アバターが両手でピースサインを出した、間違いない。会議の時くらいID表示するのが常識だと思うが、カオリにそれを期待するのは無理なのだ。こんな態度を続けて、わざわざ評価を下げる事にどんな意味があるのかと他人事ながらあきれる一方、今までよく排除されずに立ち回って来た物だと感心する。さて、会議では何か重要な事が決まった気もするし、単に次の会議の日程を決めるためだけの集まりだった気もする。だが話の内容云々は全く些細な問題だ、メンバーが一堂に集まって、会議が行われること自体が重要なのだ。参加者全員がまだ少し話し足りないな、と感じる15分で会議は終わる。 会議室を出て自分のデスクに戻る途中、カオリが近づいて来て浦島君に接触した。二人の位置データが重なると自動的に外部とのコンタクトが一時的に遮断された対会話モードに変わる。 「買い物に出ないか?」と言ってきた。 浦島君は、午後にはVRで街に出てショッピングをする予定だったので、外出自体はOKだが、なにも会社の中で仕事中に対話モードにして話す事でもないだろうに、と思い、 「昼飯の後じゃダメなのかい」と言うと、 「どうせ仕事なんて、明日にしようが明後日にしようが、どっちでも良い事ばかりだろう」と正論を述べて来た。そう言われて断る理由は見つからない。浦島君はカオリと行動を共にすることにした。 普段は出来るだけルームウォーカー(ルームランナー兼用)を使って歩くよう努めているのだが、今回はカオリの後を追跡し、ワープで商店街に飛んだ。降り立ったすぐ前の店に、探していたシャツが吊るしてあるのに気づいた。先を進んでいたカオリを呼び止める。 「ちょっと待ってくれないか。ここで買いたい物があるんだ」 カオリが振り返った。「何を買うんだ?」 「これだよ、今月だけ限定販売中のT-シャツ『禅の極み』、数量も限定なんだ」 すると、カオリが冷笑ぎみに言う。 「それ、持ってるから、お前に転送してやるよ。それにさあ、それ着るのはアバターなんだぜ。お前が現実に着る訳じゃないだろうに」 「カオリ、お前、それを言ってしまうのか」浦島君は突然、顔の前のVRゴーグルを意識する事になった。いっそのこと、今すぐゴーグルを外して自分の部屋に戻ろうかと思ったが、浦島君のその変化に気づき言い過ぎたと自覚したのだろうか、カオリが戻って来て顔を近づけて言った。 「ごめん、気を悪くしないでよ」先ほどと打って変わって哀願するような表情を見せている。最近のアバターは造りが細かくなったな、と浦島君は改めて感心した。実際、そのカオリの表情を見て、怒りは収まった。そういう反応を誘発するように設計されているんだろう。AIに体良く操られているとは思うが、それは抗えない事だ。 再びカオリは歩き出して、ある路地に入り、淡い光で照らされている建物の前に立った。浦島君はカオリが自分を連れて来た理由を理解した。WEMA (whole emotions and motions assembly)の入口で立ち止まっているカオリに言った。 「これを登録するなら、事前に伝えてくれるのが筋じゃないか?」 「いや?、かい」と小声で聞いたカオリに、「ま、いいよ」と答える。そして、カオリが登録した入館番号を自分のクラウドノートにコピーして、ゴーグルを外し、自分の部屋へ戻った。 浦島君は、ボックスからWEMAスーツを取り出し、着ていた服を脱いでそれに着替えた。WiFiをオンにすると、自動的にデイリーモニターの医療カウンセリング画面が表示される。WEMAの使用に身体的な支障が無いか、起動前にチェックを受けるのである。スーツには微細振動バイブと微小電極が全身に張り巡らされていて、皮膚知覚を刺激する仕掛けである。頭部には脳を刺激する磁気発生ユニットも付いている。この装置を身に付ければ、風や温度や匂いを感じるだけでなく、あたかも自分で動いたり触ったりしたような感覚を得る事が出来るのだ。VRゴーグルによる視覚刺激のみでは対応できないシチュエーションで使用される。例えば、格闘技、水泳、その他スポーツ、セックス、空中飛行などだ。全身を刺激しないままだと脳内リンパ還流に異常をきたすため、定期的な使用が推奨されているものの、同時に、神経にかなりの負荷がかかるので頻用しないようにとの注意も出されている代物だ。「機能チェックします。力を抜いて横になってください」という音声指示の後、体のあちこちで電気刺激が走って数分経過、モニターから「スーツの使用に問題はありません」と告げられた。浦島君はVRゴーグルを付けWEMAに入った、そして、先ほど保存していたパスワードを入力した。 カオリは先に来て待っていた。浦島君が近づくと、両手を広げて倒れ掛かって来て、二人は重なり合って倒れた。浦島君は久しぶりに人肌のぬくもりと柔らかさを知覚し、カオリの体を抱きしめた。カオリの実際の年齢が何歳かは知らない、だが、AIが作り出すその肌の感触は極上の快感を与えてくれた。 一連の共同行為を終えた後、二人はしばらく抱き合ったまま横になっていた。やがて、カオリが立ち上がり浦島君の手を引いて「今度は、あそこへ行こう」と一つのドアを指さした。そんな物があるとは、最初に入った時は気づかなかった。いびつな形の、少し不安を掻き立てる奇妙な色彩のドアだった。 「何なんだ、あれは」浦島君が尋ねた。 「もっと、面白い所さ」と、カオリは言って浦島君の背後に回り、後ろから体を押し付けながらドアの方に誘導した。 浦島君がドアノブに手を触れた時、ゴーグル画面に警告文が現れ、「ウィルス感染の危険があります」という音声が繰り返されるようになった。 「待てよカオリ、ウィルス警告が出てるぞ」 しかしカオリは「平気だよ、そんな物気にするなよ」と、更に体を押し付けた。浦島君は背中にカオリの胸のふくらみを意識しながらドアを開けた。そこは海岸だった。 波打ち際に、緑色の楕円形のボードが浮かんでいた。後ろから押してくるカオリは、浦島君をそのボードに乗せようとしているようだ。先ほどからの警告音声が気になっている浦島君は、ボードの前で抵抗を試みたが、カオリは浦島君の両手を後ろからきつく抱きしめ、その上に押し進めた。浦島君がボードに足を下ろした直後、ゴーグルが点滅を始めた。そして、 「ウィルスを確認しました、30秒後に再起動します。環境の急変に備えてください」 警告音声がカウントダウンを始めた。「28秒後に再起動します、環境の変化に備えてください・・・26秒後に・・・」 二人が乗ったとたん、ボードは沖に向かって動き出した。そして、徐々に水中に沈んでいった。再起動までのカウントを10秒以上残して、浦島君の頭は海中に沈んだ。 大きく海水を吸い込んだ、という恐怖とパニックがどれくらい続いただろうか。突然に呼吸は戻り、浦島君の周囲環境が一変した。 *** 浦島君は水と泥の広がる区画で、泥の中に足を入れて立っている。手にはまだ水に濡れた一束の苗を握っている。すぐ横に並んで立っていたカオリが声をかけて来た、「手が止まってるよ。まだ半分残ってるからね、休むのはその後だよ」手に持った苗が稲だという事は自然に分かった、作業の途中だった事も思い出した。苗の数本を右手に持ち、体を屈めてその根を泥の中に差し込む、横列に並んでそれを繰り返す。 誰かが歌い始めた。 「根付けよ、育てよ、春田の中で、伸びよ、実れよ、刈り入れの日まで・・・」 歌声は次々に増えて重なり、見事なハーモニーとなって空に舞った。浦島君も歌った、その歌はずっと以前から知っていて、繰り返し歌ったものだと理解できた。 歌いながら体を動かしているうちに、横一線に並んだ田植えの列は、端の畦道まで到達した。畦の上では別の集団が待っていた。「さあ、みんな、昼めし時だ」そう言いながら、畦道の上にゴザを敷いて、運んできた竹カゴを並べた。泥田から上がった面々は、畦道の横を流れる水路で泥を落とし、カゴの中の握り飯を掴むとゴザに座ってほおばった。浦島君も、大きな握り飯を選び出して、一つはカオリに手渡し、もう一つにかぶりついた。今まで経験したことが無いほど美味かった。他に言いようがない、働いた後の体にエネルギーがたちまち吸収される感覚だ。にぎりめしの中には塩漬けの梅の断片が入っていて、元々はほのかな飯の味を絶妙に引き立てている。浦島君はそのバランスに感心した。軽く発酵させた野菜のチップとお茶で食事を終えると、あぜ道に集った皆は立ち上がり、歩き始めた。 「昼飯の後の仕事はどうするんだ?」浦島君はカオリにささやいた。 「何言ってるんだよ、昼飯の後は休んで、それからダンスじゃないか。日暮れ前まで踊るんだよ」 そうだった、仕事の後は、今度は皆で踊るのだった。何故思い出せなかったのだろう。いやそれとも逆に、本当はそれを知らなかったはずなのに、カオリの言葉を聞いた後で以前から知っていた事の様に思い始めただけなのだろうか。ジャメ・ヴュなのか、デジャ・ヴュなのか、浦島君は一瞬判断に迷ったが、それは深く考えない事にした。隣にはカオリが居る、歌いながら仕事をして、仕事の後は踊りながら疲れを忘れる。それの何処に思い悩むべき事があるというのだ。 皆の後に付いて村の広場まで歩いた。広場に着く前から太鼓の音が聞こえて来た。やがて軽快な笛の音と、ギターのメロディーも流れて来て、それを聞いて我慢できず、歩きながらステップを踏む者も居る。広場には既に数人が輪を作っていた。集まってきた面々がその輪に加わって手をつなぎ、踊り始める。難しいステップではない。が、しばらく続けると息が弾む。少し疲れたなと思えば輪の中から出て広場の周囲のベンチに座り、手をたたいてリズムを合わせる。それを繰り返すのだ。 ひとしきり体を動かした後、汗をぬぐいながらベンチに座って踊りを眺めていた浦島君の所に、カオリが飲み物を持って来た。広場の正面にあらかじめ準備されていたドリンクは、ユズと蜂蜜の味がした。 それを飲みながら「そろそろ採蜜の時期だな」と言うカオリに、 「そうだな、そろそろだな」と、浦島君はまたジャメ・ヴュを自覚しつつ応え、養蜂の手順を思い出していた。 踊りの輪が一段落した時、広場の中央に向かって若い男女のペアが進み、そこで体を揺らしながら歌い始めた。流れるような、うねるようなメロディーだ。体を休めていた者たちが次々にこのペアの周りに集まり、彼らの動きを真似して踊り始めた。浦島君の隣に座っていた老人がつぶやいた、「海の歌だな、浜から来た若い衆か、見事なものだ。さて、明日は浜に手伝いに行かねばなるまい」 日が傾き空が赤く染まり始めると、踊りの輪は徐々にほどけて、踊り手たちは三々五々広場から去って行った。浦島君もカオリと手を組んで家に戻った。汗を流したあと、眠りにつく前に、二人は体を寄せ合って一連の甘美なパフォーマンスを繰り返した。 その夜、浦島君は奇妙な夢を見た。小さな自分が箱の中に居て、その中で形も大きさも不揃いな輪の中を行ったり来たりしているのだ。暫く動き回ると、どこかから餌が出て来て、それを食べると今度はまた別な形の輪が現れる。そしてまたその中をくぐる動作を繰り返す。それを大きな自分が箱の上から眺めていた。特別何を感じるでもなく、水が高い処から低い所に流れる様な当たり前の事として、ただ眺めているのであった。そして、更にまたもう一人別の自分が、箱を眺めている自分を見つめているのだ。そのもう一人別の自分が何を想っていたのか、目が覚めた後にはどうしても思い出せなかった。 夜明け前の涼風を感じて目を覚ました。カオリはすでに起きて、台所に居た。浦島君はあわてて起き上がった。 「ごめん。今日の当番は俺だった」 「いいよ、今朝は早く目が覚めたからさ。でも、明日の当番は交替だよ」カオリは、食卓を整えながら言った。 味噌汁と粥で食事を済ませ、浦島君とカオリは広場に向かった。広場には既に皆が集まっていた。「そろったようだな。それじゃ、行くか」中央の老人の声に皆は答え、移動を開始した。誰かが歌い始めた。さすがに、歩きながら声を合わせるのは難しい。その代り他の者は歌の合間で「ヨーイ、ヨーイ」と合いの手を入れた。一人が歌い疲れると、次の誰かが代わって歌った。そうやって浜に付いた。 浜はもう動き出していた。山から下りて来た面々は、浜の住民と挨拶し、夫々が持ち場に散って行った。「そうだった、もう何度も顔を合わせ、顔見知りになっているんだ」浦島君は思い出して、浜辺で待機している小舟に走った。船の中で作業していた浜人は、船に手をかけた浦島君に向かって声をかけた。 「丁度いい所へ来てくれた。網の準備しながら行くから、お前、櫓をこいでくれや」 「承知した」そう答えて浦島君は船の上に立ち、沖の定置網を目指して櫓をしならせた。 網の上では、先に到着していた船が箱網の締めを進めていた、海面には魚群が跳ね回っているのが見える。 「大漁だ、大漁だ、泣く子をあやす暇もない。大漁だ、大漁だ、嫁をからかう暇もない。網上げよ、櫓をこげよ、明日の天気は当てにすな・・・」網を囲んだ船の上で皆は声を合わせ、網を繰る手元に力を込めた。 浦島君が乗った船にも魚が引き上げられた。船倉が溢れそうになる前に、船頭は今度は自分で櫓を操り、浜辺に戻った。浜はさらに活気づき、持ち帰った魚が選り分けられ、次々に作業場に運ばれていく。浦島君は、数人が並んで包丁を動かしている所にカオリの姿を見つけて近づいた。 「何か手伝おうか」 「魚をさばくのは上手だったかい?」 「いや、あんまり得意じゃないな」 「それなら、網に干すのを手伝ってくれよ」 という事で、浦島君は干し網の方へ向かった。ワタを取り塩を振った魚の開きが次々に運ばれ、網の上に並べられた。ここでも皆が声を合わせて歌い、歌いながら体を動かした。 昼過ぎになって作業は一段落した。定置網の修理を終えた船も浜に戻り、海岸沿いの木陰に準備された昼食の時間となった。先ほど捕って来た魚の新鮮な刺身、焼き魚、煮魚、そして少し甘酸っぱい独特の味がする飲み物が振る舞われた。あちこちの村から譲り受けたコメを混ぜて発酵させたものだと浜人は説明した。何故か他の村で造ってもこの味は出せないのだという。発酵過程に、この土地の独特の気候が必要であるらしい。 昼食の後は皆しばらく木陰で体を休めた。軽い昼寝をする者もいた。やがて、一人二人と浜辺に下りて、波打ち際で体を動かし始めた。誰かが太鼓と鐘をたたき始める。 「踊る惚けに、踊らぬ惚け、はやす惚けも次々替われ・・・」 やがて浜辺には大きな踊りの集団が出来て、浜人も山の衆も次々に入れ替わりながら歌って踊り、疲れた者は休んではやした。踊りは夕凪の頃まで続き、そして止んだ。いつの間にか太鼓の音も鐘の音も消えて、気が付くと、浜辺に居るのは浦島君とカオリの二人だけになっている。 「あれ、他の者は何処へ行ったんだ?」 「きっと、海に帰ったんだよ」カオリが答えた。浦島君はその意味を尋ねようとしたが、カオリは意味の分からない事をしょっちゅう言っていて、その意味を問うても、たいてい答えはもっと分かりにくいのを思い出した。意味は後から考えよう、今はその言葉をそのまま頭の隅に放り込んだ。 作業と踊りの日々は続いた。浦島君は、ある時は山に入り、枝打ちや下刈りをした。ある時は果樹の手入れや果物の収穫もした。浜に手伝いにも行き、牛や豚を飼う手伝いもした。知識を確実なものにするため記録庫で読書する日もあった。読書の日も午後からは踊って過ごした。言うまでもなく、踊らないと物覚えも悪いのだ。 だが当然、風雨で作業が出来ない日もある。そんな日が続いたあとは、作業が午後になっても終わらない時もあった。 その日の作業は、珍しく日暮れまで続いた。浦島君は久しぶりの疲労感を覚えつつ家に帰って、土間で履物を脱ぐと着替えもせず床に横になった。疲労が苦痛なわけでは無い、だが浦島君はふと思い付いた考えを、隣で同じように体を横たえているカオリに向かってつぶやいた。 「なあ、今日のような仕事をもっと楽にすることは出来ないかな。たとえばさ、この間祭りで見たような、からくり仕掛けの人形が全部やってくれるとかさ」 するとカオリが、いつもより低い声で、しかしはっきりした口調で言った。 「それは言うべきじゃなかったな。NGワードだよ」 その言葉の意味を確認する前に、浦島君の周りの世界がフェードアウトした。 *** 浦島君はベッドの上に戻った。いつ外したのか知らないが、ゴーグルは付けていない。視野に入るのは、見慣れた居住ボックスの天井だ。もう一度瞳を閉じた。目をつぶると、つい先ほどまで暮らしていた海や山や、田畑の景色が鮮明に浮かんでくる。それに伴う、潮風の匂い、樹木の香り、泥にうずまる足の感触。あれは夢だったのだろうか、錯覚に過ぎなかったのだろうか。だが、それにしては記憶は非常に鮮明だ。AIが作り出す疑似知覚を、明らかに超えたものだ。 ベッドから起きて、WEMAスーツを脱ぎ、着替えた。飲み物を捜そうと冷蔵庫を開けると、リンゴが1個あった。数日前にプリントして、そのまま残していたものだ。それを取り出し、かじった。ずっと慣れ親しんできた味だ。だが、今は、これとは違うリンゴの味を思い出す事が出来る。酸味と甘味だけではない、更に豊富な味覚を持ったリンゴを覚えている。そして今は、その味を自分で作り出すすべも知っている。 半分食べかけのリンゴをテーブルに置いて、ルームランナーに乗った。位置情報をセットしVRゴーグルを付け、ガウディ通りに立つ。朝の通りを南に歩き始めた。遠くにサグラダ・ファミリアが見えて、中央にはイエスの塔が高くそびえている。朝日に反射するその塔に目を凝らした。そして気付いた。これまでは気にしていなかった画像の素子が、今は明確に認識される。この景色はVRなのだ、今までそれを知らなかったわけでは無い、だが何の迷いもなく受け入れていた。しかし今、浦島君は初めてその画像に強い違和感を覚え、ゴーグルを外した。 浦島君はリビングルームに移動し中央コンソールに座った。そして、カオリが耳元で呪文のように囁いていた言葉を思い出し、パネルにタッチして、今まで一度も使ったことが無いパスワードを入力した。 「open tamatebako」、 画面に「解除して良いですか」というアイコンが現れ、その下に警告文が表示された。 「あなたは、ドアロックを解除しようとしています。ドアを解放すると、オートファジー・コントロール・ガスが失効し、ヘルス・セキュリティが保証できなくなります。あなたの体に起こり得る変化がどのようなものか確認してください。あなたの生命予後にかかわる重大な変化です、必ず最期の項目まで確認してください。」 浦島君は、最初の数行を読み進んで顔を上げた。この文章を最後まで読んだところで、これから実行しようとしている事に対してどれほどの意味があろうか?それで決心が変わるだろうか?浦島君は椅子から立ち上がり、先ほど食べかけてテーブルに置いていたリンゴを取り、もう一口かじった。その味をもう一度確認した。 リンゴの切れ端を咀嚼しながら再びコンソールの前に立った。警告文を最後の行までスクロールし、「上記の文章を読んで理解しました」という文字の先頭にあるラジオボックスにチェックを入れた。そして、ゆっくりと指を移動し、点滅している解除スイッチにタッチした。 そのとたん部屋の明かりが消えた、今まで気づかなかった微かなモーター音が急に大きな唸り声を上げて部屋の空気を振動させ、やがて沈黙した。浦島君は、暗闇の中を手探りで歩いた。ドアの方向に進み、ドアのノブを探り当て、ゆっくり引いた。ドアがわずかに開いた時、部屋の中から外に向かって急速に空気が流れ出て、部屋の中が白い霧で満たされた。その霧はやがて大きく開いた出口から、煙の様に外にたなびき消えて行った。 浦島君は外に出た。空は青く澄み渡り、目の前には草原と、その向こうには新緑の木々が繁った森が見える。空気にも特別な刺激臭は無い。今までずっと伝えられていた外気の汚染は誇張だったのだろうか。それとも、汚染は続いているが、ヒトの感覚で感知できないだけなのか。あるいは気流の蛇行で、たまたま今は汚染された大気が離れている時なのか。だがそれはもう、思い悩むことではないと浦島君は理解した。大気の汚れを清めてくれるのはこの自然だ。ヒトはその邪魔をしないように生きればよい。 数歩進んで、浦島君は後ろを振り返り、今まで生活していた居住ボックスを眺めた。ここに住み始めたのは何時からだっただろう、思い出そうとしたが思い出せない。忘れたのか、そもそも覚えていないのかも分からない。だがそれも、もはや、どうでもよい事だ。さらに数歩動くと、光沢のある壁に自分の姿が写った。髪の毛が白くなっている事に気づいた。腕を上げて自分の手を見た。つい先ほどまでの張りのある肌ではなく、何本もしわが走り、点々と褐色のシミが見える。だが、浦島君は驚かない。これは予想していた事だ、分かっていた事だ、何も恐れるべきことではない。 浦島君は再び森の方を見た。どこからか、かすかに太鼓の音が聞こえて来る。彼は聞き耳を立て、やがて、その太鼓の音が聞こえる方向に向かって、ゆっくり歩き出した。  |