華衣 |
 by by 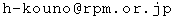 2022.06.02. 2022.06.02.--- シリーズ(たぶん) 緑恵さん、お日和はいかが #1 --- 緑恵さんは、花屋に勤めている。店の中でいつも笑顔を絶やさない看板娘だ。特別美人と言う風ではない、と思う。しかし、彼女の姿を見た者は、みんなとても幸せな気持ちを味わうのだ。それは、彼女の肌の色のせいだろうか、髪の毛の色のせいだろうか。確かに緑恵さんの肌の色は独特だ。太陽の光をたっぷりと受け止める褐色と、太陽の光をエネルギーに変換する緑色が絶妙に混ざり合っている。髪の色は鮮やかな緑色で、瞳の色も深い緑色だ。そして、彼女に近づくととてもさわやかな空気を感じ、この上なくハッピーな気持ちになるのだ。 緑恵さんが働いているその花屋はちょっと変わっている。もっとも花屋が変わっているのか、花を売っている緑恵さんが、その変わったことを自分でしているのかは良く分からない。ともあれ、その花屋で売っている花には全部薄いレースが被せられているのだ。 初めてその店を見た時には、何と奇妙な花屋だろうと訝しく思ったものだ。だが何度かその店の前を通るうちに、通勤の途中でここを歩くことが習慣になり、やがてそれが生活の中の必須項目になっていった。ある朝、唐突に店に入った。今まで自分で花を買う事などなかったのに、何だかひとりでに手と足が動いてドアを開いたのだ。中に入るとまるで新緑の深い森の中にいるような気持になった。 「いらっしゃいませ」初めて聞いた緑恵さんの声は、音楽の様にも、小鳥のさえずりの様にも聞こえて、オキシトシンとエンドルフィンが脳の中にいっぱい増えるのが分かった。親しげに何度も「緑恵さん」と言って来たが、実は彼女の名前はこの時胸につけられていた名札で初めて知ったのだった。 「何か、お探しですか?」と、一瞬ぼんやりと突っ立っていた僕に、彼女は微笑みかけて来た。 「あ、えっと、そうですね、自分の机の上が殺風景なので、何か良い物は無いかと思って」 「これから、お仕事ですか?」 「ええ、そう、そうです」そうなのだ、本当は急いで会社に向かわねばならない時間なのだ。 緑恵さんはちょっと首をかしげて考えるそぶりを見せ、「少しお待ちください」と言って、森の香をたなびかせながら小走りに店の奥へ入った。そして、小さなクローバの花を持って戻って来た。 「ムラサキツメクサです、机の上に置いてください。これは初めていらっしゃったお客様への贈り物です。また御用の際はおいで下さい、お待ちしています」そう言って緑恵さんはレースのカバーが掛けられた紫色の花を僕に手渡した。 出勤の途中だったことを思い出して気があせっていた僕は、「ありがとう」と礼を言ってそれを受け取り急いで店を出た。 何とか出勤時間に間に合って、オフィスに着いた僕は、もらったムラサキツメクサの花を鉛筆立ての中に入れた。カバーを外そうとレースに一度手を持って行ったが、なぜかためらわれて、そのままカバーをかけたままにした。 「どしたの、それ?」後ろを通りかかった同期の山野スミレがムラサキツメクサに気づいたらしく、背後から声をかけて来た。 「これね、もらったんだ」 「ムラサキツメクサだね。その花言葉、知ってる?」と、スミレが聞いて来た。僕が知るはずないだろう。当然知らないよね、という顔をして彼女は言った。 「それはね、<勤勉>よ。あなた、疲れた顔してたんじゃないの?」 そうなのか、きっと彼女は僕を励まそうとしてくれたに違いない。緑恵さんの思いやりに、僕はますます感激した。 「この、レースカバーは?」スミレは鉛筆立てを指さして聞いた。 「ああ、これは花屋さんが最初から付けてくれたんだ。そこの花屋では、全部の花にレースがかかってるんだよ。君は変だと思うかい?」 スミレはしばらく考えて答えた。 「変と思えば変。けれど、当然と言えば当然」 「何だい、それは」 「あなただって、性器を人前に晒すのはためらうでしょ。その花屋さんもそう考えてるんじゃない。面白い花屋だね」そう言って、スミレは自分のデスクへ戻って行った。 今まで、花を見てそんな事を考えたことは無かった。言われてみれば確かに、花というのは植物の生殖器だ。でも、生殖器を晒すのは何故ためらうべき事なんだ?サルは繁殖期になれば赤いお尻を見せびらかすし、鳥だって、虫だって異性に性器を見せてアピールするじゃないか。ヒトだけが生殖器を隠すようになったのだ。それは文明とやらに対する自慢、あるいはプライドのなせる業だろうか。それとも、隠すようになったことで文明が発展したのだろうか。しかし、生殖器を隠す文明が出来た後には、こんどはその隠す下着に変な執着を持つ反応が現れたりしてる。これも文明の進化なのだろうか?その日はずっとそんな事を考えていた。 それからだった、僕にちょっとした変化が起こった。今までレースの紙や布を見てもなんとも思っていなかったのに、その日からレースのカーテンやナプキンを見ると何故か変な気持ちになるのだ。そんな趣味は無かったはずだが。  目次へ |