汚染進化 |
 2021.11.21. 2021.11.21.タクシーの窓から前方に見える建物は昔のままだった。だが周囲の景色は以前とは全く違っていた。途中で見た看板には昔と変わらずGreen hillという文字が書かれているものの、丘の上は緑の部分が全く無くなり、赤茶けた土と枯れて朽ちた何本かの木の幹が残っているだけだった。 「何時からこんな風なの?」と、サキは運転手に語り掛けた。運転手はミラー越しに怪訝そうな視線を向けた。 「突然の質問で戸惑わせたかしら。この景色の事を尋ねたんだけど。」すると運転手は、依然不思議そうな表情のまま答えた。 「マム、昔からこうですよ。私が仕事を始めて以来ずっとね。」 「ああ、そうなのね。ありがとう。」サキはそう答え、改めて自分の年齢を思った。この青年には緑のGreen hillの記憶は無いのだ。 建物の前でタクシーを降り、サキは入口への階段を上った。入口のドアは今日は開放されていて、ドアの上には恐らく手作りの飾りを付けたプレートが掲げられていた。「家族開放日、これが最後の」と書かれていた。 この研究所では年に1回、職員の家族を招待してパーティーを開く日を作っていた。何日も続く実験や海外派遣などで長期間家庭を留守にする事もある、そういった家族に掛ける負担に感謝し、その理解を得るという意味を込めていた。だがそれも今日が最後だ。ここは来月閉鎖される。環境保護対策の手段を探って来た研究所は、残念ながら確実に有効な方法を見出す事が出来ず、地球の変化を押しとどめる事は出来なかった。 ホールの中央に立ってこちらを向いているカムラを見とめ、サキは近づいた。カムラの頬に顔を寄せてビズし、そのまま手を握ってサキは言った。 「ご招待ありがとう。あなたがまだ私の事を家族と思ってくれてる事にも感謝するわ。」後半のフレーズはよけいだったなと、言ってしまってから後悔した。別れてからもずっと一人だったカムラの気持ちを考えていなかったわけではないのに。 「以前のままだね。安心したよ。」カムラは昔と変わらない微笑みで答えた。 「最近は君の活動が報道されることが殆ど無くなって、さすがの君も気持ちが落ち込んでいるんじゃないかと心配していたんだ。」 「そうね、こう見えても、その傾向はあるわね。」落ち込まない日は無いわ、とサキは思った。人の目を引くため、世間の意識を変えるため、時には無茶な事もした。だが、変えられなかった。もっと無茶な過激な事をすればよかったのかも知れないと考える事もある。だが、何をしたとしても、結局変化を抑える事は出来なかっただろうという思いが浮かぶと、ますます脱力感を覚えるのだ。 「あなたの方こそ、大丈夫? あなたはあなたのやり方で努力してたじゃない。それに対する仕打ちが、研究所の閉鎖だなんて、政府は何を考えているの。」 「君からその言葉を聞いただけで、私は十分満足できるよ。」カムラは穏やかな顔で言った。昔、一緒に暮らしていた時もカムラはそうだった、とサキは思い出した。政府や企業に正しいデータを提示して説得するという彼の正攻法では世界の動きを元に戻す事は出来ないと、悩んだ末決断し彼に別れを告げた時も、その穏やかな表情で受け入れてくれた。 「他の職員はどうなの? ここを閉鎖するという方針に抵抗する声は無かったの?」 「異議を唱えたのは、最長老の私と、副所長のアダムスだけだったよ。多勢に無勢さ。」 「アダムスもまだ居たのね。彼は今日は何処に居るの。久しぶりに会ってみたいな。」 「アダムスは2日前に辞表を出して、自分の国へ帰ったよ。まだできる事があるかもしれないと言ってね。彼の熱意には頭が下がる。」 サキが研究所をやめると言った時、思いとどまるように何度も説得に来たのがアダムスだった。そのアダムスが最も強烈に、研究所閉鎖に抗議したという事か。あの時の彼の思いを今改めて推察して胸が熱くなり、「そう・・」と言った後サキはしばらく押し黙って、中庭の方を眺めた。そこには若い研究員たちとその家族が和やかに語り合っているのが見えた。その姿を見てサキは口を開いた。 「あの人たちは、何も言わなかったの? 研究の結果を世間に公表して変化を押し止めようとは思わなかったの?」 「君は、最近の研究所のレポートを見ていないようだね。」カムラは少し寂しそうな表情を浮かべ、答えた。 「ごめんなさい、実はそうなの。」これで、自分の気持ちの落ち込み様を白状したようなものね、とサキは思った。 「例えば昨年、政府から最高評価を受けた論文のタイトルは、こうだ。<地球環境変化に伴う医療費伸び率の予測>、どんな結論だったか想像できるかい?」 「たぶん、私の頭では想像できないような内容なんでしょうね。」 「保健衛生に関して君や僕のようなグレタ世代がが論じていたのは、環境悪化による健康被害だった。けれど最近の論点は違うんだ。環境が悪化した状態で・・・いや、彼らは環境悪化とは言わず環境変化と言ってるがね、その状態でいかに医療経済を適正化するか、という事が重要視されるんだ。結論はこうだ、環境が変化すれば病気の者は状態が急速に進行する。だから、治療を緩和療法に切り替えれば、重症期が短くなり、高額な医療費が使われる時間も短縮できる、とね。」 それを聞いたサキは、息を詰まらせ、一呼吸おいてからカムラに問いかけた。 「まさか、あなたは、その論文が公表されるのを認めたわけ?」 「もちろん私に見せられた素稿段階では却下したよ。だが、いつの間にか査読通過して印刷されていた。もうこの動きは私には阻止できないんだ。」 信じられない、という風にサキが頭を振る姿を見ながら、カムラは続けた。 「さらにダメ押しの論文も教えよう。それは、<環境変化に無関心な者ほど心の安寧が保たれる>というものだよ。」 それを聞いてサキは、ある憚られる単語を短く小声で吐き出した後こう言った。 「あのジョーカーが選挙運動の時に使った、<すべて受け入れろ、そうすれば心は穏やかだ>というやつね。」そしてまた先ほどの単語を吐き出し、ため息をついた。 2人は庭園に向かって開いた扉の横にある椅子に座り外を眺めた。研究所の開設時には、庭園のあの噴水の周りには季節を彩る草花が植えられ、その背後にはドングリから育てられた木々が小さな森となって、忙しい仕事の合間を和ませてくれた。だが、今そこのヒビ割れた土の上に並んでいるのは廃材を組み合わせた奇妙なオブジェ達だ。噴水の庭の向こうに見える池は、昔の澄んだ水ではなく、何処かのパイプラインから漏れ出たオイルが一面に黒く浮かんでいる。その池のそばで、集まってランチテーブルを広げている職員たちの姿に気づき、サキはカムラに聞いた。 「あの子たちは、あの油だらけの水辺が気にならないのかしら。」 「彼らは気にならないらしいね。むしろ奇麗だと言う者さえいるよ。」 「なんという事なの。」そう言いながらサキは椅子から立ち上がり、扉に近づいて眩しそうに庭を見た。 その時、小さな女の子がサキのスカートを引っ張った。 「おばちゃん、これ何?」 その少女が指さしているのは、パーティションの影に一部隠れた壁のポスターだった。片隅が剥がれた古いポスターは、開設時に撮影された研究所の風景を印刷したものだ。少女の興味を引いたのは庭の花を写した写真だった。サキは少女の横にしゃがみ、一緒にその写真を見つめた。 「これはね、ルージュ・ピエールっていうバラの花よ。」 「ふうん・・」とつぶやいて暫くその写真を眺めていた少女は、サキの方に向き直って言った。 「きれいだね。」 サキは思わずその少女を抱きしめた。涙があふれて止まらなくなった。 「そうよ、まだこんな子供たちが居るじゃない。自然の美しさがどんなものか知っている子供たちが、まだ居るのよ。」 初めて会った見知らぬ老女が抱きついて来て泣きじゃくるのを、面食らった表情で見つめている少女を、これ以上驚かせてはいけない、そう考え、カムラは近づいて、ゆっくりとサキを少女から引き離した。走り去っていく女の子を眺めながら未だ涙しているサキの両肩にそっと手を添え、しかし、冷酷な現実を更に伝えるべきかどうか、思い迷っていた。サキの周りに集うのは、ほとんどが汚染されていない人々であろう。だから事態がどれほど進んでいるのか分かっていないのかも知れない。 バラの花をきれいだと言ったあの少女のDNAには、これから環境変化が容赦なく襲い掛かる。彼女が成人するまでに広範なメチル化が進行し、代謝が変化した脳と体は、草木や花や静かな海や青空を美しいとは感じなくなるのだ。そして、熱波に焼かれ嵐で吹き飛ばされた砂だらけの大地や、プラスチックで覆われた浜辺を愛するようになり、やがて油と火薬と肉の腐敗臭を、全く不快な物と思わなくなって行くのだ。 まるで、そのカムラの考えを読み取ったかのようにサキはつぶやいた。 「心の安寧を選んだ彼らに祝福の言葉を送るつもりはないわ。変化をそのまま受け入れる事が正しいとは絶対に言わない。私はこれから、もっと激しく抗う。たとえ私の考えが、いずれ消えていく古い思想だと言われても。」 そして、振り返った。 「カムラ、あなたは?これからどうする?」 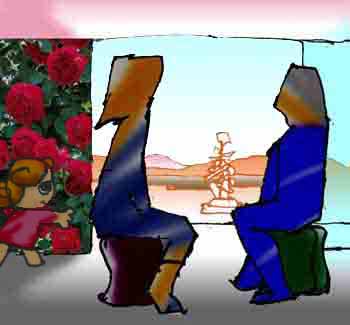
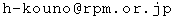 目次へ |