難解な酵母 |
 by by 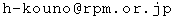 2021.07.17. 2021.07.17.「かたつむりが、まっすぐな刃の上を進んでいくのを、見ていた・・・まっすぐな、刀の刃だ・・・」その後言葉なのか唸り声なのか分からない音、続いて、「かたつむりが、まっすぐな葉の上を進んでいくのを、見ていた・・・まっすぐな、葉っぱだ・・・」そして、前とは少し違った唸り声。 確かに遠藤の声だ、だが何の事を言っているのか分からない。それに、Facenoteに投稿された彼のビデオはあまり良くない装置で撮影されたらしく、画像も音声も、とにかく不鮮明だった。 「それが彼の一番新しい投稿だ、先月の29日。それまでにも同じ動画が投稿されたことがある。どんな意図があるのか不明だ。発信場所も特定されていない。だが、現地のガイドがおおよその位置を推定しているので、現地に着いたらそのガイドと共に行動してもらう事になる。」営業部長はノイズばかり大きくて効きの悪いエアコンにイラついた様子で扇子を動かしながらそう言った。 「もう一人、君の同行者を紹介しよう。」部長はテーブルの端に座っていた目つきの鋭い男の方に手を向けた。最初に部屋の中に入った時から、一人だけ場違いな感じを持って居た男だ。男はゆっくり立ち上がって俺の方に会釈した。「私の事は”ケイビ”と呼んでくれ。」と彼は言った。「それは名前ですか?苗字ですか?」俺が尋ねると、「警備員の”警備”だ。呼び捨てでも”警備さん”でもどちらでも構わない。」と答え、「以上だ。」と会話を終了した。窓の外では待機したヘリが主軸のエンジンを回転させ始めた。 最後に部長はこう言って話を終えた。「本社からの指示は君も受け取っていると思うので、詳しくは繰り返さない。君の任務は彼を探し出して資料を受け取るか、その入手方法を聞き取る事だ。もしも彼がその資料を他社に転売しようとしているのなら、それを阻止する事を考えてほしい。手段は制限しない。」俺は先ほど渡されたカバンの中身を思い出し、この部長は本当に俺にあれを使わせる事を考えているのだろうかと、何度目かの悪寒を覚えつつ外に出た。逆に外は肌が焼けそうな熱さだ。飛び立つのを待ち構えていたヘリの中に、俺は駆け込んでいった。 ヘリの窓から眼下のジャングルを眺めながら遠藤の事を思い出していた。遠藤とは大学の同じクラブで知り合い、卒業後同じ製薬会社に就職した。理学部の彼は研究部門に、経済学部の俺は営業に配属され、お互いの生活はすれ違う事が多くなったが、それでも時間が取れれば一緒に飲みに行く仲が続いた。遠藤がこの地に送り込まれたのは1年半前だ。出発の前の晩、2人だけで済ませた送別会の席で彼は自分の派遣の理由を語ってくれた、本当はこれは秘密事項なのだと断りながら。 遠藤がこのジャングルに派遣される事になったきっかけは、現地支社長が目にした地方新聞の小さな記事だった。一時期武装ゲリラのメンバーだった青年がジャングルの中で、チェ・ゲバラと行動を共にしたことがあると言うある部族の長老に会った。長老の年齢は優に100歳を超え今なお矍鑠としていた。部族の中には他にも100歳を超える者が何人もおり、その健康の秘訣は部族に長く伝わる特別な酒だと話した、というものだった。支社長は、この「特別な酒」という言葉が気になり本社に連絡して来たと言うわけだ。 エチルアルコールは、その摂取量に比例して脳細胞を萎縮させる事が分かっている。しかし一方で少量の、と言っても普通我々が軽くたしなむ程度の量の飲酒ならば、アルツハイマー病のリスクを軽減させるというデータも存在する。この矛盾するデータを明瞭に説明できる機序は分かっていない。いや、分かっていなかったと言うべきか。我が社の研究部門で調査を続けていたグループが、この機序を説明できるかもしれない発見をした。まだ仮説の段階であるが、それは、エチルアルコールと共に合成される、まだ正体が良く分かっていない別の成分が、アルツハイマー病のリスク低減にかかわっているのではないか、というものだ。その正体不明の成分を効率的に産生する酵母を、他社がそれに気づく前に捜し出す事が、会社の重要な課題となっていた。ここの支社長からもたらされた情報の中の「特別な酒」はその有力候補と判断され、遠藤が送り込まれた。 現地支社の社員と共に、新聞記事に書かれていた元ゲリラの青年を捜して数か月経った頃、「有力な情報を仕入れた」と周囲に語った数日後に遠藤は姿を消した。情報が途絶えて1年後、彼が昔使っていた古いアカウントでFacenoteに動画を投稿している事に研究部門の後輩が気付いた。そして、遠藤と親しかった俺が追跡役として呼び出される事になった。 ヘリは川上に向かって飛び、見渡す限りジャングルに囲まれた川の中州に着陸した。ここに来てさえ対岸は何百メートルも先にしか見えない、さすがに大河だ。広い中洲には補給用の施設が建設されていて、俺たちはその夜はここに泊り、翌日ボートで更に川上に向けて出発する事になった。ここで新たにガイドが加わった。サントスと名乗るその男はよくしゃべる奴だった。”警備”は相変わらず無口なので、その相手はもっぱら俺が受け持った。 翌朝まだ薄暗い中、”警備”が操縦するボートに乗り込んだ。船尾に繋がれたもう一台の小型ボートに気づき”警備”に尋ねると、あれはサントス用だとの返事が返って来た。サントスにも聞いたところ、「Sim、俺の船さ」とだけ答えて微笑んだ。ボートの上でもサントスは俺に良く話しかけて来た、というより、一方的に彼の仕事や職場仲間の事をしゃべった。仕事場で彼は料理担当をしている事、肉の調達に苦労した事、料理の好みが違うので口論になった事、あるいは少し個人用に横流しした事など、本当かどうか分からないが、いろいろ話してきた。俺がだんだん返事に疲れて、あいまいな相槌しか打たなくなっても、彼は気にせず話した。 その日の夕方にはボートを岸に係留し、船の上で食事を摂った、当然料理担当はサントスだ、後部デッキに座りガスボンベを使って肉料理を作ってくれた。小さな鍋の上で器用に調理した、横で音楽をかけながら。かけていた曲目は、今ではクラッシックとなったローリングストーンズだ。何かの思い出があるのだろうかと想像したが、結局その事は聞きそびれた。料理の味はまあまあだ。「美味いよ」と言うとサントスは嬉しそうに礼を言い、職場仲間は礼を言って来ないなどと、またお喋りを始めた。だが翌日、目的の場所に近づいたと思われる頃からサントスはあまり喋らなくなった。 俺には、どこまで行っても同じジャングルに見えるが、どうやってそれを見分けるのか、川べりに少し空間のある場所でサントスはボートを岸に着けるように指示した。俺たちは船を降り、岸辺の大きな木の幹にロープを繋ぎ、さらにもう一本川べりにアンカーを打ち込んで繋いだ。そしてサントスの後に続いてジャングルの中に踏み入った。そういう目で見れば確かに、そのルートは周囲と比べて立ち木も立ち草も少なく、川に続く道のようでもあった。しばらく歩くと開けた場所に到達した。そこには木の葉で屋根と周囲を覆った大小の小屋が建っていた。サントスは広場の端で立ち止まり、両手を丸めて口に当て、広場の中央に向かって何か叫んだ。すると小屋の一つから3人の男が現われ、こちらに歩いて来た。シャツを着ている者も居れば、腰みのだけの半裸の者も居る。一人はゴムサンダルらしいものを履いているが他は素足、と、まあてんでばらばらの格好である。サントスは先頭の男に両方の手のひらを上げて見せた後、相手に話しかけた。彼はあまりこの部族の言葉に堪能ではない様子だった。恐らく俺たちが、ここに日本人の男が来ていないか捜しに来たと説明しているのだろう、俺たちの方を何度か指さしながら身振り手振りで語り、相手の返事を何度か確認した後俺に向かって尋ねた。「ここによそ者が1年近く住んでいると言ってる。会ってみるか?」 俺たちは部族の3人組の後に続いて建物が集まる広場の中央に歩いて行った。先頭の男がそのうちの一つを指さして何か言った。「あの中だと言ってる。」サントスが通訳した。俺は木の葉に囲まれたその小屋の中に入った。中で座って作業をしていた男がこちらに振り返り、びっくりした顔で俺を見た。俺の方もその姿に驚いた。髪の毛も髭も伸び放題、汚れた短いズボンを履いただけ。しかし以前より少しやせてはいたが遠藤に間違いなかった。「遠藤か。」 「あ、ああ。」彼は戸惑ったような言い方で返事した。 俺は遠藤に近づき、その手を取った。「元気で良かった、良かった。」そう言いながら何度も握った手を振った。涙が出てくるのをこらえられなかった。だが遠藤は、久しぶりに再会した俺の姿を見ても、なぜか嬉しそうなそぶりを見せなかった。 小屋の入口で様子を見ていたサントスが俺に声をかけて来た。「セニョール、探してた人に会えたようだから、俺は帰るよ。これから7日程度はゲリラもこっちには来ないはずだ。けれど、その後は分からない。あんた方もそれまでに帰った方が良いよ。それじゃ、アデウス。」そう言って足早に広場の向こうに姿を消した。俺はあっけにとられてサントスの後ろ姿を追っていたが、”警備”はこの事をあらかじめ知っていた様子で驚いたそぶりも見せず入口に立っていた。 俺は遠藤の方に顔を戻した。「どうしたんだ遠藤、やっと見つけたのに、まるで迷惑だとでも言うような顔じゃないか。」そう言うと遠藤が答えた。 「そりゃ、懐かしいさ。だけどな、今はタイミングが悪い。村の人たちの様子が朝から変だったのは、君たちが来たからなんだな、今分かった。こんな遠い所まで探しに来てくれた君たちには申し訳ない言い方だが、来てほしくなかった。」 「なんだよそれは、随分な言い方だな。」俺は少々声を荒げたが、遠藤はそんな事は意に介さない様子だった。 「1年かかって、やっと言葉と仕草が一致しかかって来た所だったんだ。もう少しで彼らの言葉が理解できそうな所だったんだ。だが、君たちが来たことで村の人の態度が変わってしまった。また振出しに戻ってしまったかも知れない。」そう言って頭を抱えてうつ向いた。彼の落胆の様子はうかがい知ることは出来るが、しかし、俺たちがはるばるここまでやって来たのは何故か、それは伝えなければならない。 「例の酒は見つかったのか?」 「Yesでもあるし、Noでもある。」遠藤はうつむいたまま答えた。 「おい遠藤、真面目に答えろよ。」今度は俺の声の調子に気づいたのだろうか、遠藤はゆっくり顔を上げて言った。 「酒は見つかった、酵母も分かった、だがあの酒を飲むだけでは効果は無いんだ。それを飲む時に khaewefhnorする必要があるのさ。」しかし、その単語は今まで聞いたことが無い奇妙な発音だった。 「いったい何なんだ、そのkヘヴェ・・何とか、とは。どういう事なんだよ。」 「khaewefhnorとしか言いようがない、他の言語では表現できないな。日本語で言えば”カタツムリの動き”に関係した表現のように思うんだが、まだ良く分からない。けれどね、その言語を理解できるようになったら、誰にでも出来る簡単な事だと分かるはずだ。説明できなくてじれったいが、これは現地の人達と生活してその言葉を理解する以外に方法は無いんだ。khaewefhnor出来ない者は、この酒を飲んではいけないと言われて俺はまだ飲ませてもらっていない。言葉が分からないよそ者には長寿の効果は無いんだ。」 「この部族以外には効かないという事か? それは、ホントの所は遺伝子の問題とか、ここの環境や独特の食べ物とかが関係しているんじゃ無いのか?」 「違うね。」遠藤は即座に否定した。「1年ここに居て、他の場所で生活しているここの部族の何人かを見て来た。逆にここで暮らしている他の部族の者も観察して、この酒とkhaewefhnorする事がセットになって初めて効果が出る事を確信した。」そして、続けた。「だから、俺はまだ帰らない。ここの人たちの言葉が理解できるまでここに居る。もし、khaewefhnorする事がどういう事なのか理解出来るようになったら、そしたら帰るかもしれない。いや、どうだろうな。実の所、ここの生活は俺は嫌いじゃないんだ。」 俺は返す言葉が見つからず黙っていた。 小屋の前でいきさつを見ていた村人の一人が入って来て遠藤に話しかけた。しばらく対話した後、遠藤が俺たちに向かって言った。 「君たちを昔の友達だと紹介したよ。今夜の食事を提供するそうだ。この人が村のナンバー2のマラビさんだ。年齢は103歳になる、信じられるかい。」現地の人の年齢は元々分かりにくいが、確かに50歳と言われても納得しそうな体つきだった。 俺たちは広場の中央にある一回り大きい小屋に案内され、そこで数人の村人と共に、提供された食事を食べた。何かの種類の芋を蒸したものや肉を焼いたものが提供された。質素な味だが、これらはここでは特別な料理なのだと遠藤は解説した。食事の後は、その小屋の隅の敷き藁の上で寝るようにと言われた。遠藤は、「村の人には、君たちは明日ここを出ると説明している」と俺たちに念を押して自分の小屋に引き上げて行った。 興奮して寝付けないのではないかと思っていたが、いつの間にか眠っていた。目を覚ました時、隣の小屋で”警備”が遠藤と言い争っているのが聞こえた。 「お前のたくらみは読めてるぞ。この酒を他の会社に高く売りつけようとしてるんだろう。アルツハイマーの特効薬なら今後膨大な利益を稼ぐことが出来るのは分かっている。金か、それとも、その会社の重役にしてやるとでも言われたか。」 「何度言えば分かるんだ、これは物質だけで解決できる方法じゃないんだ、カギになるのが言語なんだ、むしろ文化なんだよ、文明なんだよ、」遠藤が必死に説明しているのが俺には分かった。 「その下らない言い訳は聞き飽きた。お前が見つけた酵母はこれか?このドブロクか?」"警備"の怒鳴り声の後、何かが倒れる音がして、"警備"がその中をかき回しているらしい音がした。 「やめろ、khaewefhnor出来ない者がそれを飲んではダメだ。」 遠藤がそう叫んだ後、2人が取っ組み合いを始めた音がした。俺は慌てて床から起き上がり、暗闇の中、足元を探りながら出口に近づいた時、"警備"が壺を抱えて戻って来た。隣の小屋へ向かおうとした俺を制止し、「戻るぞ。」と俺の肩を掴み、俺に何の反論もさせないまま外に押し出して、川の方向に歩き始めた。暗闇の向こうには明らかに人の気配がした。俺たちを遠くから取り巻き、後を追って来るのが感じられた。彼らが俺たちに何か仕掛けてくるのかも知れないという不安から2人とも何も喋らず、星明りだけを頼りに手探りで川辺に進んだ。止めてあったボートに乗り込み、エンジンをかけず手漕ぎで岸から離れた。星明りを通して、川岸の木陰にヒトの動く姿が確認できたが、彼らはそれ以上追って来なかった。 川の流れに従って暫く下った所で、俺はやっと声を出すことが出来た。「遠藤はどうした?」 「あいつは来ない。それだけだ、もうあいつのことは聞くな。」今まで以上に威嚇するような低い声で"警備"は言い、その後は何も話しかけてこなかった。 ボートは翌日の夕方に川の中流の中州に戻り、そこに待機していたヘリで空港まで飛んた。ヘリの中で"警備"が、持っていた壺を俺に押し付けてこう言った。「空港で副社長が待っている。これはお前から副社長に渡せ。お前の仕事だ。」俺は黙って受け取った。 空港で待っていたプライベートジェットには、副社長と研究室主任が待機していた。空港の個室で簡単なパスポートのチェックを受けてジェットに乗り込み、程なくして機体は離陸した。 キャビンの中で俺は研究室主任に酒が入った壺を渡した。主任は中身の半分をアルミボトルに移し替えて密封し、残りの液を細かく小瓶に分注して、それをディープフリーザーの中にしまった。 「ご苦労だったね、この後は研究室で分析して培養増殖するだけだ。」 そして、壺を振り中身を確認して副社長に話しかけた。 「副社長、なぜか少し余ってしまいました。飲んでみますか?」 「うん、そうだね。無駄に捨ててはもったいないからね。」副社長はそう言ってグラスを2個取り出し、壺に残った酒を注ぎ分けた。俺の方に向かい「君は現地で飲んでいるだろうから、主任と私で試飲してみるよ。」と言って、グラスを机の上に置いた。俺はこの時になって遠藤が言った言葉を思い出した。 「待ってください。それはただ飲むだけではダメなんです。」 「ダメというのは、どういう事かね?」副社長が不機嫌な声で問いかけて来た。しかし、遠藤が言っていたあの言葉を再現する事は俺には出来なかった。 「それをですね、飲む時に、呪文が必要らしいんです。」 「呪文?君は何を言ってるんだね。」副社長はますます不機嫌になった。俺が手を伸ばす前に、グラスを上げて中身を飲み干した。 「どういうかねえ、甘酒の中にカビを混ぜたような味だな。」副社長の言葉に、自分も飲み終えた主任が「そうですねえ。」とうなづいて答えた。 10分ほど経過した頃、副社長が胸のあたりを抑えながら苦しそうな表情をして椅子から立ち上がり、床に倒れこんだ。横の席では主任も椅子に座ったままぐったりしている。気づいた"警備"が自分の席から飛んできて副社長の所に駆け付け、腕をとり脈をみて言った。「不整脈だ。」そして、俺の方を向いて「早く副社長の胸をはだけろ。」と指示し、前方の椅子の下からAEDを取り出してきた。機械をセットし胸にコードを張り付けて通電した。脈を確認し、もう一度AEDを使った。脈が戻っていないと判断すると、心マッサージを始めた。しかし副社長の心臓は回復しなかった。 2人の体をキャビンの床に並べた後、"警備"は腕の時計を見て「サン・ホセまであと2時間だ。」と言って自分の席に戻った。自分がやるべきことは全てやった、という雰囲気がありありと分かる。 あの酒を渡したのは俺だ、それはキャビンの監視カメラに記録されている。真っ先に俺が何かをしたと疑われるだろう。だがあの酒と、酵母の分析が進めば事実は分かる、それで俺が会社に留まる事が出来るかどうかは別にしても。そしてその酵母は、人体に有害な毒と言うレッテルを貼られて葬り去られるだろう。遠藤が現地の人たちの中に住んで、その効果を発揮させる言語を会得しようとしていた努力は、報われる事なく消え去る。だがもしも、その酵母がサン・ホセに到着しなかったら、そして、先ほどキャビンで起こった出来事が誰にも知られる事なく消えれば、そうなれば、事態は変えられるかもしれない。人類に多大の貢献をするであろうあの酵母を捜しに、また別の誰かが現地に行き、そのうちの誰かが現地の言葉を会得する可能性が残る事になる。 俺のシャツのポケットには、万が一の際に遠藤に使うようにと会社から渡された揮発ガスの小さなボンベが残っている。この機体の狭い空間を、キャビンもコクピットも数十分間満たすには充分な量だ。ジェットがサン・ホセに到着するまでに、片が付くだろう。 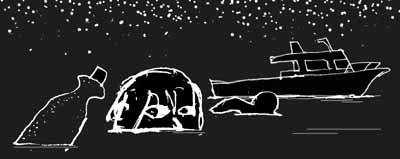
目次へ 蛇足1:これを読んで、コッポラ監督のあの映画の場面を思い出された方があれば、・・そうです、そのイメージを散りばめてます。 蛇足2:抗マラリア薬のキニーネ、手術に欠かせない筋弛緩薬のスキサメトニウム(旧称サクシン)、など、いわゆる「未開の先住民」と言われる人たちが使っていたものから貴重な医薬品が発見されたことは今まで何度もありました。今なお我々が知らない薬や治療法があるかもしれません。それを伝える現地の言葉が失われていくことに警鐘を鳴らす論文があります。Language extinction triggers the loss of unique medicinal knowledge、Rodrigo Camara-Leret and Jordi Bascompte、PNAS June 15, 2021 118 (24) e2103683118 |