非限の夢 |
 by by 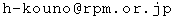 2021.05.04. 2021.05.04.「先月は大変だったね。」私は宮本の少しやつれた顔を見ながら言った。 「うん、まだご家族との話し合いが終わってないんだよ。ご両親は、実験中に何か特別な事をしていたのじゃないか、という疑いをずっと持っておられてね。学部長も一緒に説明してくれたんだけど、完全に納得されていないようなんだ。」 「そうか・・」と小声で相槌をうつ。ベッドで休んで脳波を測定するだけの実験に参加したはずの子供が、心停止となり、何とか蘇生出来て徐々に回復してきたと思ったら、1ヵ月後突然に行方不明になったと言われれば、確かになかなか納得できないかもしれない。 「でもね、今日来てもらったのはそれとは別の事なんだよ。」宮本は思いを切り替えるように言った。「脳神経生理学者としての君の意見を聞きたいんだ。ちょっとデータを見て欲しい。」そして、私を隣の実験室へ連れて行った。 部屋の中には、心理学研究室には不釣り合いとも言える大型コンピューター装置が並べられていた。宮本は壁面に何台も設置されたスクリーンの前に座り、データを呼び出した。 「これは、彼の脳波なんだよ。隣の部屋で観察していた研究員が心電図と呼吸の異常に気付いて、すぐに心マッサージと人工呼吸を始めたんだけど、慌てたせいで脳波記録装置のスイッチを切らないまま蘇生術を始めたんだ。他の教室員もやってきて30分近く蘇生を続けた。そしてその間の脳波がずっと記録されていた。」ディスプレイに解析図を表示させて、宮本は話を続けた。 「記録していた脳波は、電極を64倍に増やして、スーパーハイレゾルーションで採取された物なんだ。それをコンピューターで周波数解析した。それが、これだ。」宮本はディスプレイの画面を指さしながら言った。「脳波の周波数分布を見てくれ、ここからだ。この時彼の瞳孔反射が消失していることを確認している。その後、脳波が高周波にシフトして行くんだ。最初は徐々にだが、変化は等比級数的に進んで、ここからはこの装置では検出できないレベルになっている。」 彼が言っている意味を理解できず、私は尋ねた。「それって、どういう意味。」 「それを知りたいんだよ。ひょっとしたら、脳の時間の流れが変化しているんじゃないか、そんな事を考えてるんだ。」 宮本を見る私の顔が、かなり懐疑的な表情を見せていたのだろう、少し慌てた調子で言った。 「分かってる、変な事を言ってると思ってるだろ。でもね、これを見てくれ。」今度は机のファイルボックスから分厚いコピー記録を引っ張り出した。 「蘇生が成功して意識が回復した後3日間、ほぼ眠った状態だった。目を覚ました彼は、猛烈な勢いであの日の記憶を書き残し始めたんだ。それがこのノート。ノートの本体はご両親に返して、これはコピーだけどね。彼は22歳なんだが、あの蘇生の間に、その後の人生を経験したらしい。所々多少ぼんやりした部分はあっても、大部分は非常に鮮明な記録になっている。」 私はコピーファイルを手に取って開いた、それは彼の未来の日記であった。ほぼ毎日の記録が残されている。大学を卒業して、中堅の工作機械の会社に就職し、海外に出張してそこで研究者として過ごす・・。 「だけど、これは彼の創作なんだろ?」私が聞くと、宮本は答えた。 「当然そう思うよね。けれど、そこに出てくる会社や海外の研究者は実在しているんだ。海外の研究者の名前は、僕もそれを見てから調べて初めて知った。まだ有名じゃないけど新進気鋭の研究者達だ。今の段階では彼が知るはずは無いと思うんだよ。それだけじゃない、彼は50歳で心筋梗塞で死亡するらしいんだが、その後、今度は彼が生まれた時からの日記に変わるんだよ。これもかなり克明な記録になっててね、例えば、彼が生後3か月の時に熱を出して往診してもらった、その病院の先生の名前も書いてあるんだけど、ご両親も覚えていなかったその名前は調べてみたら正しかった。小さい時に父親が乗っていた自家用車のバックナンバーも、正しかった。もちろん彼のお父さんも覚えていない数字だよ。想像で書いたものじゃないんだ、彼の生涯の正確な記録なんだよ。」 その説明を聞き、私はコピーから目を上げて聞いた。 「うん、これは一つの事案として考えよう。これとさっきの脳波の件とは、どう関係があるの?」 宮本は、コピーの最後のページを開いて私に示し、言った。 「彼の記録は、彼が私の教室に来て、脳波解析の研究に協力するため記録を開始する所で終わっているんだけど、その後こう書いてるんだ。ここに、ほら。」 最後のページには、「この後、僕の人生が永遠に繰り返された」と書いてあった。 「この言葉をそのまま解釈すれば、彼は自分の50年間の人生を、あの蘇生術の十数分間の間に、永遠に繰り返した、という事になる。」宮本は最後のページを指さしたまま続けた。 「彼の単なる錯覚だろうか。それとも、もしも脳の活動が急速にスピードアップして無限大に近づいて行ったら、周囲では10分あまりの時間でも、彼の脳の中では無限大の時間が流れて行ったのではないだろうか。脳生理学的に、それは可能だと君は思うかい?」 「シナプスの間をアセチルコリンが通過するには、一定の時間を要するよ。」私は答えた。 「でも、もしもだよ、アセチルコリンがシナプスの末端から顔を出すだけの電位変化が認識できるようになったら・・いや、もっと小さく、分子の小さな揺らぎを変化として認識できるようになるとしたら、どうだろう。」 「それが大脳皮質の広い感覚野で知覚されるのは難しいだろうな。」 「いや、皮質まで電気信号が伝わる必要はないんじゃないか?海馬のごく小さな範囲で。」宮本は自分の考えを必死で納得させようとしている様に思えた。 「宮本、少し冷静になれ。この花圓君の日記は、彼が思い出して書いたんだ。人の記憶は極めてあいまいなものだ。他人に語ったり記録に残した記憶というのは、既に自分の経験で解釈、改変されたものに変わっているという事は、心理学者の君の方が良く分かってるだろう。」 「もちろん知ってる。だけど、彼の記憶は経験で改変された物じゃなかった、さっきそれを説明したよな。」 私は返事に詰まった。「うーん、けれど、あまりにもSF過ぎるぞ。それに、脳波の周波数変化というのも、この花圓君だけの特殊な変化かも知れないし。」 「別の脳波を見せよう。」宮本はそう言ってディスプレイに新たなデータを展開した。 「これは、先週亡くなったオヤジの最後の脳波だ。いよいよ最後と言う時に病棟からここにベッドを移して脳波を記録したんだ。病棟の医者や看護婦からも、うちの教室員からも非難囂々だったが、最終的には協力してくれた。息が停まって、心停止して、瞳孔が開いた後、脳波は高周波にシフトして行った。花圓君と同じパターンで。」 宮本は私の方に振り返った。「亡くなった人の意識は、消えることなく永遠にその脳の中で持続している、そういう事にならないか?」 「まるで、ゼノンのパラドックスだな。」私はつぶやいた。 「そういう風にも言えるね。で、あの矢はどうなる?そこで止まる訳じゃないよな。オヤジが死んで、それで特に思うようになったのかも知れない。君は笑うだろうが、こんな事も考えてるんだよ。死んだ人の意識は、我々とは違う別の次元に飛んで行くんじゃないか、ってね。」 そして、真剣な顔でこう言った「あの花圓君は、ひょっとしたら、彼がこれから生きるはずの別の次元に行ったのかも知れない・・」 
目次へ |