発恋の香り |
 by by 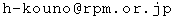 2022.06.12. 2022.06.12.--- シリーズ 緑恵さん、お日和はいかが #3 --- 「ここにあるバラの花、全部、適当に包んでよ」 テレビでよく顔を見る、派手な噂が絶えないタレントの声だ。高飛車な言い方だな、と思いながら僕は店頭の方を見た。 「どなたかへの、贈り物でしょうか」 緑恵さんは、いつもと同じ笑顔で対応している。 「そう。向こうが言うにはね、アクセサリーやドレスじゃ満足しないんだそうだ。で、俺も考えたわけよ。それじゃあ、花にしてみようかってね。ここら辺の花屋を全部まわってさ、バラの花搔き集めてるの。ほら、誰かの歌にもあるじゃん、あれよ、あれ。というわけで、急いでくれるかな。次の店にも行くんだからね」 「失礼な事を言ったとしたら、申し訳ありません。けれど、バラの花にもたくさんの種類があるんですよ。色も香りもそれぞれ違いますし・・・」 「ああ、そんなのは、いいのいいの。質より量よ。こんなに金かけてんだぞ、ってとこ見せつけてやれば、それでいいの」 緑恵さんの顔は、今まで見たことが無い険しい表情に変わり、押し黙った。男はそれには全く気付くそぶりもなく、店の前で待機していたマネージャーらしき人物を手招きした。そして、 「ここにあるバラをさ、全部買って車に運んでよ」と言って出て行った。 替わって店に入ったマネージャーが、「それでは、この品を買い取らせていただきます」と並べられていたバラの花を両手に抱えて持ち上げようとすると、黙っていた緑恵さんが声を出した。 「ちょっと待ってください。全部無くなると、後から来られたお客さんにご迷惑をおかけしますから、少しだけ残しておいてください」 「それもそうですな」と手を止めたマネージャーの腕の中の、バラの束の中から、緑恵さんは何本かの赤いバラを選りだして別の容器に入れた。 店の前の車の中から件のタレントが大声でどなった。 「その、変なカバーは外しといてよ。後で外すのめんどうだし」 「承知しました」と言って、マネージャーはバラの花を覆っていたレースを一つずつ剥がした。それを棚の横に積み上げ、「代金は、後で事務所の方に請求書送って下さい」と言って去った。 店の奥に座り一部始終を見ていた僕は、机の向かいに座っているマスターに小声で話しかけた。 「嫌な気分ですね」 「でも、お客様はお客様ですからねえ」マスターは寂しげに答えた。そして、僕たち2人は気を取り直し、机の上の書類を眺めながら今度の企画についての相談を再開した。 しばらくして、若い男が店に入って来た。 「いらっしゃいませ」 緑恵さんは、いつものほほ笑みと森の香りを取り戻し、対応した。 「あの、今日彼女に会うんです。それで、赤いバラを贈ろうと思ったんですけど、何処を捜してもバラの花が無くて・・」 「承知しました。特別のバラの花をお分けしますよ」緑恵さんは、先ほど選り分けたバラの花に近づき、もう一度香りを嗅ぎ、その中の1本を包んで、その男に渡した。 彼が少し不安げに「これ、1本だけで良いでしょうか。僕の気持ち伝わるでしょうか」と言うと、緑恵さんは答えた。 「大丈夫です。ただし、これだけは守ってください。お二人で一緒にこの花の香りを嗅いでください。それだけ、忘れないでくださいね」 そして、1輪のバラを持って店を出て行く男の後ろから。「きっと、うまく行きますから」とつぶやいた。 これを見ていた僕は、たぶん不思議そうな顔をしていたんだろう、それに気づいたマスターが僕の方に体を寄せて、解説するようにささやいた。 「あの男の人の恋は、必ず成就しますよ。あの人が買って行ったバラの香りは特別なんです」 「え、どういう意味です?」 「花の香りはね、同じ株から出来た花であっても全部違うんですよ。蕾ができて開花するまでに、周囲の環境から受ける影響がそれぞれの花に個性を与えるんです。日の当たり方や風向き、DNAのメチル化など、様々なものが関係するんでしょうけどね。それで、時には、特別な香りの花が育ちます。緑恵さんはその違いを嗅ぎ分ける事が出来るんですよ。さっき彼女が選んだ、あのバラの花は、間違いなく恋のキューピットの香りを放っているはずです」 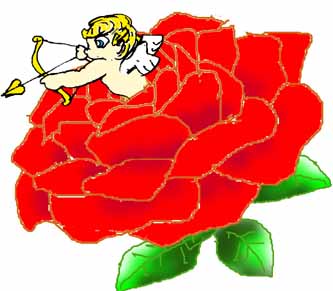 目次へ |